「自分のお墓をどうするか?」
「自分には子どもがいないので、この先お墓は誰が見てくれるのだろう…」
現役の葬祭ディレクターとして私自身、こうした不安を抱える方々を数多く見てきました。
そして私自身も後継者のいない身として、このお墓の問題に直面しています。
今回の記事では、同じ悩みを抱えるあなたのために、永代供養と樹木葬の基礎知識から、後悔しないための選び方まで、私の経験と専門的な知見を交えて徹底的に解説します。
この記事を読めば、あなたの不安が解消され、自分にとって最適な供養の形を見つけることができるでしょう。
あなたに最適な供養方法を見つける3つのステップ
ステップ1:遺骨をどうしたいのか考える
ご遺骨を単なる「モノ」と捉えるか、「供養する対象」と捉えるかで、選択肢は大きく変わります。
遺骨を単なる「モノ」と捉えることができれば、遺骨を拾わないという選択肢もあります。
この場合は、火葬場を管轄する市町村などの自治体が遺骨を供養します。
供養する場所は火葬場により異なるので、心配な方は確認しておきましょう。
*この方法は関西などエリアが限定されているようです。
ただし、親族に「遺骨=供養する対象」と捉える方がいると必ず反対されます。
事前の十分な話し合いが非常に重要になります。
ステップ2:永代供養と樹木葬は何が違う?|基本の比較
「後継者がいない」という悩みから、「永代供養」と「樹木葬」を検討される方が非常に多いです。
これらは混同されがちですが、以下のような違いがあります。
永代供養
寺院や霊園などの管理団体に、遺骨の管理と供養を永続的に任せる方法です。
樹木葬
桜などの特定の樹木の根元に遺骨を埋蔵する方法で、墓石の代わりに樹木を墓標とします。
樹木葬の詳しい解説はこちらをご参照ください。
樹木葬は永代供養の一種として扱われることが一般的です。
樹木葬の他にも永代供養の方法はあり、法律や手続き、費用面で違いがあります。
それぞれの特徴を理解し、自分に合った方法を選びましょう。
ステップ3:費用や管理面で後悔しないための選び方
永代供養には、費用や管理方法によって様々な種類があります。
合祀(合葬)型
合祀(ごうし)もしくは合葬(がっそう)と呼び、最も費用を抑えた方法です。
遺骨を骨壺から取り出して他の方と一緒に納めるので、返してもらえません。
公営と民営の霊園、お寺など、選択肢が最も多い方法でもあります。
大阪の一心寺の「骨佛」、四天王寺の「納骨総祭塔」も合祀型です。
・大阪の公営霊園での永代供養についてはこちら
納骨堂型
お寺や霊園などの建物の屋内に、遺骨を収蔵する方法です。
屋内なので天候を気にせずお参りでき、駅近の場所も多く、車がなくても気軽にお参りできます。
施設により、線香など火を使用できなかったり、お参りできる時間が決まっている場合もあります。
一定の期間(30年など)を過ぎると、別の場所で合祀されることもあるので、契約の際には注意が必要です。
デメリットは建物の管理費がかかるので、合祀型より高額になります。
個別墓型
一般的なお墓のように、家族や夫婦で入ることができます。
永代供養なので年間の管理費が不要ですが、契約後は追加で入ることができない場合があります。
契約する前に、誰が入るのか事前によく考えておかなければなりません。
【注意点】散骨は誰でもできる?|知っておくべき法律とマナー
遺骨を海や山に撒く「散骨」も選択肢の一つです。
厚生省の「散骨に関するガイドライン」において『節度を守った散骨』であれば、法的に問題ないと発表しています。
・海洋散骨の解説についてはこちら
法律とマナー
遺骨は形状を視認できないよう粉状に砕かなければなりません。
遺骨と分かる状態で散骨すると、刑法第190条の遺骨遺棄罪で処罰の対象になります。
近所の公園や港などではなく、人里離れた海域や山林で行う必要があります。
専門業者の利用
散骨できる場所を探したり、遺骨を砕く作業はハードルが高いため、専門の業者に依頼するのが一般的です。
最後に|最も大切なこと
後継者がいないお墓の問題は、単なる手続きではありません。
残される家族や、あなた自身の「人生の終わり方」について考える大切な時間です。
最適な方法は人によって異なり、後悔のない方法を選ぶのは時間がかかります。
どの方法を選択するにしても、一人で抱え込まず、家族や信頼できる人と十分に話し合うことが何よりも重要です。
自分にとって安心できる、後悔のない方法を探しましょう。
私自身がどのような方法を選択するのか決まっていません。
実際に色々と現地に行って、自分の目で確かめようと思います。
今回の記事が、自分にとって安心できる、後悔のない方法を探すためのきっかけとなれば幸いです。
ご意見・ご指摘などございましたらお問い合わせフォームからお願いします。
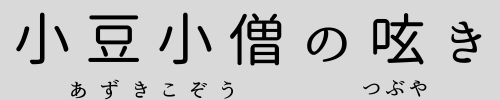
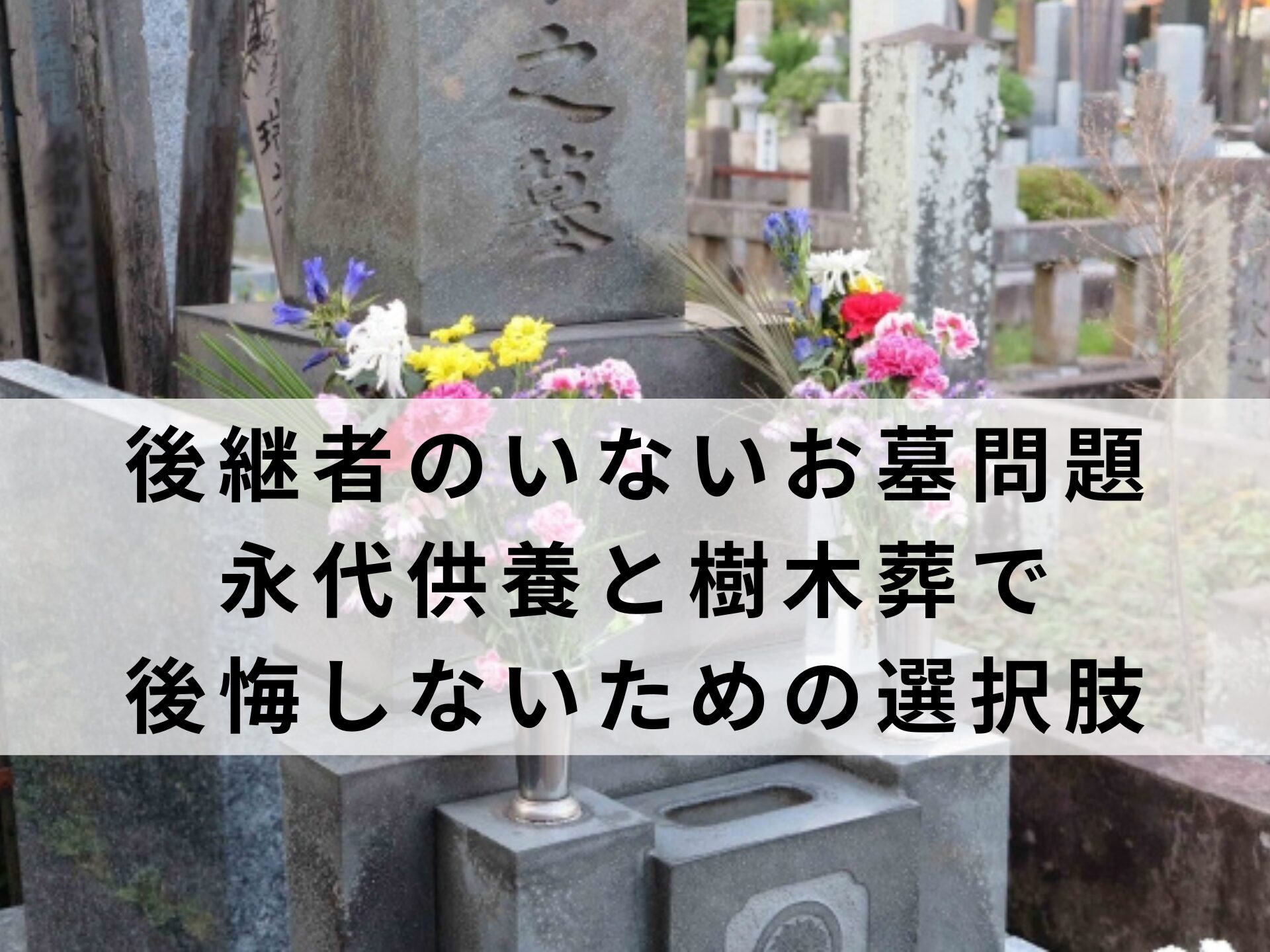
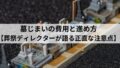
コメント