「遠方のお墓をどうすればいい?」
「後継ぎがいない…」
「子供はいるが墓のことで迷惑をかけたくない」
多くの方が抱えるこのような悩みを解決するのが「墓じまい」です。
しかし、ご先祖様のお墓を処分することに抵抗を感じたり、手続きの複雑さに躊躇される方も少なくありません。
今回の記事では、現役の葬祭ディレクターである私が、墓じまいの費用相場から具体的な進め方、そして後悔しないための注意点までを徹底解説します。
本記事は、特定の霊園や石材店などと提携しておらず、純粋に利用者様の立場から正直な情報をお届けします。
複雑な手続きをスムーズに進め、ご家族・ご親族が納得できる「墓じまい」を実現するためのポイントを、葬儀屋の視点から分かりやすくご案内いたします。
墓じまいとは?その定義と知っておくべきこと
「墓じまい」とは、お墓に納められている遺骨を取り出し、墓石を解体・撤去し、墓地の使用権を管理者に返す一連のプロセスを指します。
墓じまいは単なる墓石の撤去だけでなく、取り出した遺骨をどこに供養するのか(改葬先)まで含めて考える必要があります。
ご先祖様への感謝を表し、残されたご家族が安心して供養を続けられるための重要な選択です。
墓じまいにかかる費用相場と具体的な内訳
墓じまいは複数の工程に分かれるため、総額がいくらになるのか想像しにくいものです。
ここでは墓じまいにかかる費用相場と具体的な内訳を解説します。
費用相場の目安
墓じまいの総費用は、約50万円~300万円が目安とされています。
このように価格差が大きい理由は、都心部か地方のような地域差ではありません。
墓地の立地、広さ、墓石の大きさ、改葬先の種類によって大きく変動します。
費用の内訳と確認ポイント
主な費用の項目は以下の通りです。
- 閉眼供養・開眼供養料(お布施):
- 目安: 3万円~10万円(閉眼供養)、3万円~10万円(開眼供養)
- ポイント: お付き合いのあるお寺がない、金額が不明な場合は、事前に確認しましょう。インターネットで僧侶派遣サービスを利用することも可能です。
- 離檀料:
- 目安: 0円~数十万円(寺院墓地の場合のみ)
- ポイント: 法外な金額を請求されないよう、丁寧に事情を説明することが重要です。
- 墓石の解体・撤去費用:
- 目安: 10万円~30万円/㎡(墓地の広さ、墓石の大きさ、作業の難易度で変動)
- ポイント: 墓地の指定業者がある場合は、必ずそこに依頼が必要です。
複数の石材店(3社ほど)から見積もりを取り、適正価格か判断することが重要です。
安すぎる見積もりは不法投棄などのリスクも考えられるため注意しましょう。
- 行政手続き費用(改葬許可申請手数料など):
- 目安: 数百円~数千円
- ポイント: 自身で行えば費用は抑えられますが、時間や手間がかかります。
- 遺骨の取り出し・洗浄費用:
- 目安: 3万円~10万円(墓石の解体を依頼する石材店に依頼しましょう)
- ポイント: 遺骨の状態によっては洗浄や乾燥が必要な場合があります。
- 改葬先(新しい供養先)の費用:
- 永代供養墓: 5万円~150万円(合祀、個別型など形態で変動)
- 樹木葬: 10万円~80万円
- 納骨堂: 20万円~150万円
- 散骨: 5万円~30万円
- 手元供養: 数千円~数十万円
- ポイント: 最も費用が大きく変動する部分です。
どのような供養をしたいか、家族と話し合って決めましょう。
墓じまいの具体的な進め方(全9ステップ)
墓じまいは複雑な手続きが必要ですが、順序立てて進めればスムーズに完了できます。
以下の9つのステップを参考にしてください。
ステップ1:親族の同意をもらう
あなたがお墓の継承者でも、自分自身の判断のみで「墓じまい」を進めてはいけません。
何も知らない親族がお墓参りに行ったら、お墓がなく更地になっていれば、親族同士のトラブルの元になります。
「墓じまい」を検討した段階で、家族だけでなく親族にも説明をして同意をもらいましょう。
ステップ2:遺骨を移す場所(改葬先)を決める
取り出した遺骨をどこで、どのように供養するかは、墓じまいを考える上で非常に重要です。
永代供養墓、樹木葬、納骨堂、散骨、手元供養など、多くの選択肢があります。
※各供養方法の概要は、別の記事後継者のいないお墓問題|永代供養と樹木葬で後悔しないための選択肢を参考にしてください。
永代供養は大阪の公営霊園でも可能なので、詳しくは以下の記事をご確認ください。
・大阪の公営霊園で永代供養|失敗しない選び方
・大阪北摂霊園の樹木葬について
遺骨を自然に還したいとお考えの方は、海洋散骨の費用と種類を徹底解説|後悔しないための全知識もあわせてご検討下さい。
ステップ3:お墓の管理者に墓じまいすることを伝える
改葬許可の手続きには、お墓の管理者から「埋蔵証明書」(お墓の形態によって「埋葬証明書」「収蔵証明書」になります)の発行が必要です。一般的な霊園であればスムーズに進みます。
しかし、お付き合いのあるお寺の敷地内にお墓がある「寺院墓地」の場合は注意が必要です。
墓じまいに至る事情を丁寧に説明し、理解を得るように努めましょう。
ステップ4:改葬許可申請書を作成する
墓じまいをするには、納められている遺骨を取り出し、他の場所に移すための「改葬許可書」が必要です。「改葬許可書」は、お墓のある役所が発行します。
そのためには、お墓に納められている人数分の「改葬許可書申請書」の提出が必要です。
「改葬許可申請書」の書式は、インターネットで『お墓のある役所の市町村名』+『改葬許可申請書』で検索してダウンロードできます。
検索できなければ役所の窓口でもらえ、大抵の場合、申請書の提出から受理まで数日かかります。
記入には以下の情報が必要となります
- 死亡者の本籍
- 死亡者の住所
- 死亡者の氏名
- 死亡者の性別
- 死亡年月日
- 埋葬もしくは火葬の場所
- 埋葬もしくは火葬の年月日
- 改葬の理由・場所
多くの情報を人数分を用意しなければなりません。
時間をかければ自身でも用意することが可能ですが、行政書士などの専門家に依頼する方法もあります。
ステップ5:「埋蔵証明書」と「受入証明書」を取得する
お墓の管理者から 「埋蔵証明書」
改葬先の管理者から「受入証明書」をもらいます。
ステップ6:「改葬許可書」を発行してもらう
「改葬許可申請書」「埋蔵証明書」「受入証明書」などを役所に提出し、「改葬許可書」を発行してもらいます。
ステップ7:お墓を撤去してくれる業者を探す
墓じまいには、墓石の撤去や更地化の工事が必要となり、石材店に依頼することが一般的です。
墓地に指定の業者があれば、必ずその業者に依頼しなければなりません。
ステップ8:閉眼供養と遺骨の取り出し
墓石を撤去する前に、お坊さんに「閉眼供養」をしてもらいます。
その後は依頼した業者に遺骨の取り出しを任せましょう。
ステップ9:お墓を撤去して、墓地を管理者に返還する
閉眼供養を済ませて、遺骨を取り出しているので、撤去工事は依頼した業者に任せて問題ありません。更地になっているのを確認して、管理者に墓地を返還して完了です。
墓じまいで後悔しないための注意点【葬祭ディレクターの視点】
墓じまいは、法的な手続きだけでなく、ご家族・ご親族の心理的な側面も考慮しなければなりません。葬祭ディレクターとして、私が特に注意していただきたい点をお伝えします。
親族とのトラブル回避が最優先
普段は付き合いのない親族も、そのお墓にお参りをされているかもしれません。
墓じまいを検討した段階で、家族だけでなく親族にも状況と理由を説明し、同意をもらいましょう。
もしかしたら、お墓の後継者になってくれる親族がでてくるかもしれません。
離檀料請求トラブルへの備え
お付き合いのあるお寺の敷地内にお墓がある「寺院墓地」(寺墓)の場合は注意が必要です。
長い期間にわたり敷地内で先祖の供養をしてきた繋がりが寺院にはあります。
墓じまいしなければならない状況と理由を丁寧に説明しましょう。
不十分な説明のせいで、墓じまい=檀家を辞めると捉えられ、法外な離檀料を請求された事例があります。
安易な専門家選びに注意
改葬許可申請書の作成は、基本的に申請者が行わなければなりません。
撤去工事を依頼した石材店や墓地の管理者が行うことは、行政書士法で禁止されています。
申請者自身が行うことが困難だと判明した場合は、費用がかかりますが行政書士などの専門家に依頼しましょう。
まとめ
今回は「墓じまい」について、費用から具体的な進め方、注意点までを葬祭ディレクターの視点から解説しました。
墓じまいは、ご先祖さまの象徴である墓を処分するという心理的な負担が非常に大きい決断です。
しかし、遠方のお墓の管理負担、後継者不在、経済的な理由など、墓じまいを検討せざるを得ない現代社会の背景もあります。
大切なのは、ご家族・ご親族全員で話し合い、
「どのような供養を望むのか」
「誰にどのような負担をかけたくないのか」
2点を明確にすることです。
複雑な手続きや費用に関する不安は、一人で抱え込まず、信頼できる専門家(行政書士、霊園、そして私たち葬儀のプロ)に相談してください。
今回の記事が、あなたが後悔のない「墓じまい」を検討する一助となれば幸いです。
ご意見・ご指摘などございましたらお問い合わせフォーム、下記のコメント欄からお願いします。
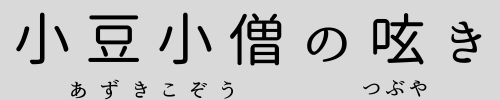
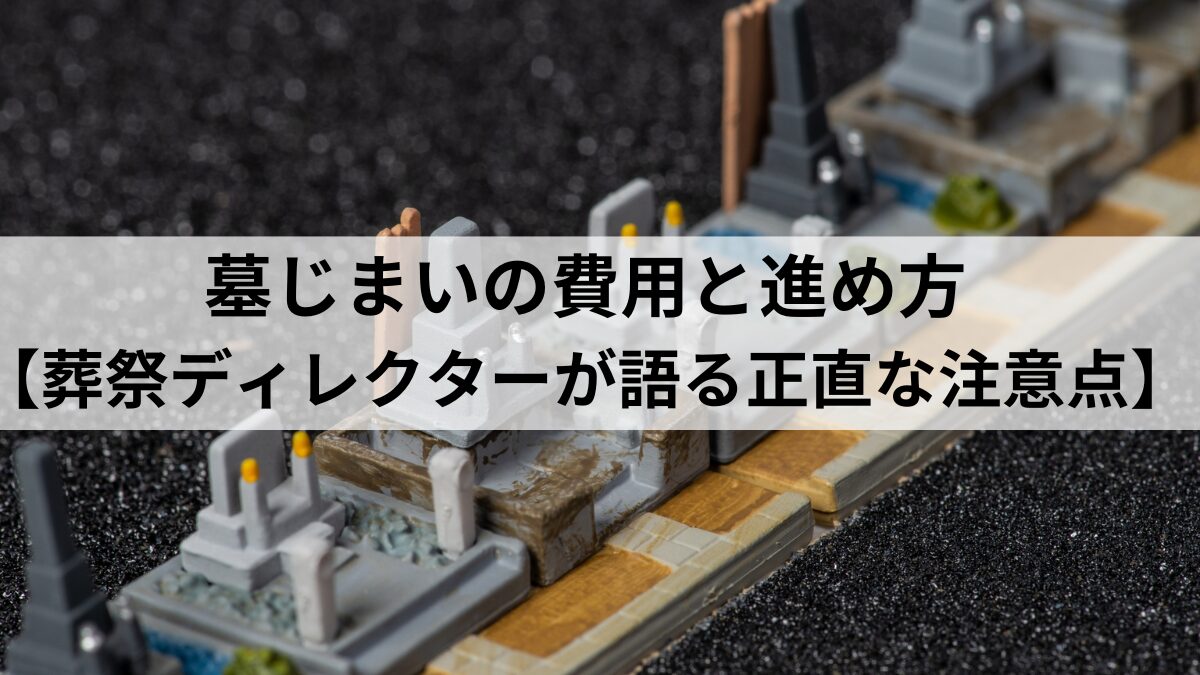
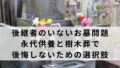

コメント