大切な故人様との最期の別れ。
その際に、親戚や葬儀社のスタッフから「末期の水(まつごのみず)」という言葉を初めて耳にする方は少なくありません。
- 「どういう意味があるの?」
- 「正しいやり方や作法が分からない…」
- 「うちの宗派でも必要なの?」
初めて聞く言葉なので、上記のような疑問や不安を抱くことは自然なことです。
今回の記事では、現役の葬祭ディレクターである私が、末期の水の意味や由来から、準備物、具体的なやり方・作法、さらに浄土真宗などの宗派での方法までを徹底的に解説します。
「やらなかったらどうなる?」といった心配事にも寄り添い、故人様を後悔なくお見送りするための知識を網羅。
後悔のない最期の儀式のためにご一読ください。
末期の水(まつごのみず)とは?その意味と由来
末期の水という儀式が具体的にどのようなもので、なぜ行われるのか、その由来から基本的な知識まで掘り下げます。
末期の水とはどんな儀式?読み方と具体的なやり方
「末期の水」は、「まつごのみず」と読みます。
文字通り「末期(臨終の際)」に故人様の口元を湿らせる儀式を指し、日本において古くから行われてきた大切な風習の一つです。
「死に水」と言われることもあります。
この儀式は、医師から臨終が告げられた直後、故人様の体が温かいうちにご遺族や近親者が行うのが一般的です。
新しい脱脂綿(または筆や鳥の羽)などを水で湿らせ、故人様の唇を優しく潤します。
故人様への最期の看取りの行為として、故人様への感謝と安らかな旅立ちを願う家族の想いが込められています。
故人を潤す最期の儀式:末期の水に込められた意味と由来
末期の水には、単に故人様の喉の渇きを潤すという物理的な意味だけでなく、精神的・宗教的な深い意味合いが込められています。
その起源は、仏教の開祖であるお釈迦様の故事に由来するとも言われています。
故事によると、お釈迦様がご入滅される際、激しい喉の渇きを訴えられた際、羅刹女(らせつにょ)という女性が尼蓮禅河(にれんぜんが)の清らかな水を捧げ、その渇きを癒したという「尼蓮禅河の聖水」の故事が伝えられています。
この故事にならい、故人様が安らかに旅立てるよう、生前の苦痛や渇きを和らげ、喉を潤すことで三途の川を渡る準備とする。
あるいはこの世への執着を断ち切り、迷いなくあの世へ向かえるように願う、との深い意味が末期の水には込められている心の区切りとなる重要な儀式です。
末期の水はいつ、誰が、どこで行う?適切なタイミングと参加者
末期の水は、故人様への最期の看取りの儀式として、適切なタイミングと作法で行われることが望ましいとされています。
- 行うタイミング(いつまで)
医師から臨終が告げられた直後、まだ故人様の体が温かく、息遣いが感じられるうちに行うのが一般的。
法的な期限や仏事の法事のように「いつまで」という決まりはありませんが、一般的には速やかに行うため葬儀社が到着する前、ごく親しいご家族だけで行うことが多いです。
心理的・身体的な余裕や準備する道具がなければ、葬儀社の安置室に移動してから行うこともあります。 - 行う場所
故人様が息を引き取られた場所、例えば病院の病室・ご自宅・介護施設などで行われます。
静かで落ち着いた環境で、ご遺族が故人様と向き合える場所が選ばれます。
病室など逝去された場所で行えなかったら、安置した場所で落ち着いたタイミングで行っても問題ありません。 - 参加者(誰が)
末期の水は、故人様を最も身近で看取ったご遺族(配偶者や子、孫など)が行うことが一般的です。具体的な順番や作法の詳細は、次の章で詳しく解説します。
末期の水の基本的なやり方・作法【準備物から手順・回数まで】
宗旨や地域により準備物など差はありますが、ここでは一般的な流れを解説します。
準備するもの
- 水
水道水で構いませんので清潔な冷水を、コップや湯飲み茶碗などに汲みましょう。 - 割り箸・脱脂綿、またはそれに代わるもの
故人様の口元を湿らせるために使います。
割り箸の先に新しい清潔な脱脂綿(ガーゼ・清潔な布でも可)を巻いて白糸や輪ゴムで縛って固定します。故人様の唇に直接触れるものですので、必ず清潔なものを選びましょう。
地域によっては、鳥の羽や新しい筆などを用いることもあります。
葬儀社が専用の綿棒などを用意することもあるので相談してみましょう。 - 樒(しきみ)や菊の葉(葉っぱ)
地域やご家庭によっては、水に樒の葉や菊の葉を浮かべて、葉っぱの先で直接口元を湿らせたりする場合もあり、葬儀社が用意することもできます。
樒は仏教で用いられる植物で、清浄を意味するとともに、邪気を払うとされています。
菊も日本においては古くから高貴な花とされ、樒と同じように邪気を払う力があると考えられています。 - その他: 水を含ませた後、故人様のお顔を拭くための清潔なタオルなども準備しましょう。
「酒」は使う?水以外の液体について
末期の水は、その名の通り「水」を用いて行うのが基本的な作法です。
しかし、「故人が生前、大変お酒が好きだったから最後に…」といったご遺族の想いから、「水以外の液体、酒などは使ってはいけないのか」と疑問に感じる方もいらっしゃるかもしれません。
基本的な作法では水が原則です。仏教的な意味合いにおいて「水」は清らかさや苦しみを癒す象徴として捉えられます。
しかし、故人様への弔意や愛情の表現として、「酒」「ビール」などで代用することもあります。
私自身も末期の水を「水」でなく、故人が飲みたかった飲料で代用したことは多くありました。
自宅や葬儀式場では問題ありませんが、病院や介護施設によっては管理上の理由から、水以外の液体の使用が制限される場合がありますので、施設側へ確認することが不可欠です。
お坊さんを呼ばない宗教儀礼を省略する葬儀では、故人が好きだった「酒」「コーヒー」などを水の代わりに使うことは増えているので、葬儀社の担当者に相談してみましょう。
誰が、どのような順番と手順で行うのか
末期の水は、故人様とご遺族にとっての最期の交流の時間です。
心を込めて丁寧に行うことが大切で、具体的な作法や目安を知っておくと安心して儀式に臨めます。
- 誰が行うのか:故人様と血縁の深い方から
末期の水は、故人様と最も血縁の深い方から順に行うのが習わしです。
一般的には下記の順番です。
- 配偶者(妻または夫)
- 故人の子(長男・長女から順に)
- 故人の親
- 故人の兄弟姉妹
- 故人の子の配偶者
- 故人の孫
- 従兄弟・従姉妹や叔父叔母など、その他の親族
ご遺族が全員揃っていない場合は、到着を待ってから儀式を執り行うのが一般的です。
ただし、到着が大幅に遅れる場合などは、すでに揃っているご遺族・親族の中で、上記の順番に従い儀式を進めることもあります。
なお、幼い子どもにまで無理に末期の水をとらせる必要はありません。子どもの年齢や状況を考慮し、ご家族で判断しましょう。
病院や葬儀社のスタッフから案内があれば、それに従うようにしてください。
- 回数:
末期の水を行う回数の厳密な規定はありませんが、血縁の深い方々から、それぞれ1回ずつ行うことが一般的です。
同じ方が複数回行うのは好ましくないため、たとえ気持ちがあっても控える必要があります。
一人ひとりが故人様への感謝や、安らかな旅立ちを願う気持ちを込めて、丁寧に儀式を行うことが最も重要ですし、故人様もそのお気持ちを受け取ってくださることでしょう。
「何回行わなければならない」という回数にこだわるよりも、一人ひとりが故人様への感謝や、安らかな旅立ちを願う気持ちを込めて、丁寧に行うことが大切です。
具体的な手順:安らかな旅立ちを願う丁寧な作法
末期の水は故人様への看取りとして、静かに、そして慈しみの心をもって行われます。
以下に、一般的な手順と注意点をご説明します。
*あくまでも一般的な手順なので、地域の風習に通じている方がいれば、素直に教えてもらいましょう。
- 心を落ち着かせ、準備を整える
まず、故人様を囲むご遺族は、静かに心を落ち着かせましょう。
準備した水と脱脂綿などを故人様の枕元に用意します。もし病室や施設で行う場合は、周りの状況にも配慮し、静かに行える環境を整えます。 - 順番に故人様の口元へ
血縁の深い方から順に、故人様のお顔の近くへ進みます。
脱脂綿などを水に浸し軽く水滴が落ちない程度に絞り、葉っぱを使用する場合は、葉の先端に水を含ませます。 - 優しく唇を湿らせる
湿らせた脱脂綿や葉っぱを、故人様の上唇の左から右になぞるように動かし、次に下唇の左から右に、同じように優しく触れていきます。
無理に口の中に入れたり、多量の水を含ませる必要はなく、唇の表面を軽く濡らす程度で十分です。
この時、「お疲れ様でした」「安らかに」「ゆっくり休んでね」など、心の中で故人様への感謝や、安らかな旅立ちを願う言葉をかけながら行うと良いでしょう。
ご遺族にとって故人様と向き合う大切な時間となります。 - 全員がやり終えたら、故人様のお顔を清める
その場にいる全員が末期の水を行い終えたら、故人様のお顔をきれいに拭いて終了します。
顔の拭き方は、まずおでこから(左から右へ)優しく拭き、次に鼻の部分を上から下へ拭きおろし、最後に顎のまわりを左から右に拭きます。
顔を拭く際も故人様を労わる気持ちを込めて声をかけてあげましょう。
病院や施設の場合、備え付けのタオルなどを使用するよう指示されることもあるので、確認してください。
宗派などによる末期の水の違い
「末期の水」は仏事なので、浄土宗や曹洞宗など宗派を超えた共通の作法ですが、特定の宗派・他の宗教では異なります。
【浄土真宗】末期の水を行わない理由と代わりの方法
末期の水は仏教の儀式として広く行われますが、浄土真宗においては、原則として末期の水を行わないのが一般的です。これには、浄土真宗の独自の教えが深く関係しています。
浄土真宗では阿弥陀如来の「他力本願」の教えに基づき、「亡くなった方は、すぐに阿弥陀如来の力によって極楽浄土に導かれ、仏になる(往生即成仏)」とされています。
故人様は苦しみなくお浄土に行かれるため、この世からの手助けは不要という考え方です。
末期の水でなく、僧侶を招いてお仏壇の前で「臨終勤行」をあげていただく流れになります。
お付き合いのある寺院があれば、一報を入れて「臨終勤行」のタイミングを相談しましょう。
ただし、地域によっては長年の慣習として、浄土真宗のご家庭でも末期の水を行う場合もあります。
ご自身の宗派が浄土真宗である場合は、葬儀社やご寺院(宗教者)に確認することをお勧めします。
神道では?
神道においても仏教と同様に故人の口元を湿らせる儀式を行いますが、その意味合いと作法は異なります。
神道では死を「穢れ(けがれ)」と捉えるので、故人や遺族を清めることが重視され、末期の水は穢れを祓うための儀式と位置づけられます。
仏教で用いる脱脂綿や樒の代わりに、「榊(さかき)の葉先」を水で濡らし、故人様の口元を湿らせるのが一般的です。
キリスト教では?
キリスト教においては、末期の水という儀式は行われません。
キリスト教では、死を「神のもとへ帰ること」と捉え、安らかな旅立ちを信じるため、仏教のような特定の意味合いでの「末期の水」は必要としないのが一般的ですが、キリスト教独自の儀式が行われます。
カトリックの場合は、臨終の際に神父が聖書を朗読しながら、故人の額と両手に聖油で十字架をしるし、罪の許しを請う「病者の塗油の秘跡(びょうしゃのとゆのひせき)」という儀式が行われます。
プロテスタントの場合は、臨終に牧師が立ち会い、パンとぶどう酒を与える「聖餐式(せいさんしき)」を行うことがあります。
臨終後、ご遺族の希望や地域により仏教の「末期の水」に似た形で故人の口元を湿らせるような行為が行われる場合もありますが、これは教義に基づくものではなく、あくまで個人的な看取りの行為に近いと言えます。
末期の水は「やらなかったらどうなるか?」近年の選択肢
「末期の水」は大切な看取りの儀式ですが、必ず行わなければならない義務ではありません。
近年では様々な理由から末期の水を行わない選択をするご遺族もいらっしゃいます。
葬儀社の担当者の知識や経験が浅ければ、「末期の水」の案内がないかもしれません。
- 「やらなかった」場合の心配
もし末期の水を行わなかったとしても、故人様への供養が不足する、不謹慎であるといったことは決してありません。故人様への感謝と、安らかな旅立ちを願う気持ちが大切です。
末期の水だけが故人への感謝と気持ちを表す方法ではないので、後悔する必要はありません。
- 末期の水を行わないケース
ご遺族の意向・故人の生前の希望: 故人様が生前に従来の習俗を望まなかったり、ご遺族が特定の儀式にこだわらない選択をしたりすることもあります。
病院や施設の状況: 医療機関や介護施設によっては、感染症対策や衛生管理の観点から、末期の水が制限されたり、所定の用具を使用するよう指示されたりする場合があります。
宗教・宗派の教義: 前述の浄土真宗のように、教義として末期の水を行わない宗派もあります。
末期の水は、故人様とご遺族の大切な触れ合いの機会です。形式に囚われすぎず、ご遺族が納得し、故人様を心安らかにお見送りできる方法を選ぶことが要です。
もし迷いや不安がある場合は、遠慮なく葬儀社のスタッフやご寺院にご相談ください。
まとめ
今回は「末期の水(まつごのみず)」について、その由来・意味から、準備物、具体的な作法や手順、そして宗派や宗教による多様な考え方まで、現役葬祭ディレクターの視点から詳しく解説しました。
末期の水は、単に喉の渇きを潤す行為に留まらず、故人様への感謝を捧げ、安らかな旅立ちを願う、非常に大切な儀式です。
お釈迦様の故事に由来するその歴史的背景を知ることで、儀式に込められた意味をより深く理解できたのではないでしょうか。
故人様との関係が深い方から順に行うことや、無理に口を開かせず優しく唇を湿らせる、といった具体的な作法、浄土真宗のように末期の水を行わない宗派があること、神道やキリスト教では独自の看取りの儀式があることなど、様々な知識をご紹介しました。
最も大切なのは、故人様への「ありがとう」の気持ちと、安らかな旅立ちを願う心です。
末期の水を行うかどうかにかかわらず、ご遺族が故人様を心から大切に想い、後悔なくお見送りできる選択をすることが何よりも重要です。
今回の記事について、ご意見・ご指摘がございましたらお問い合わせフォーム、下記のコメント欄からお願いします。
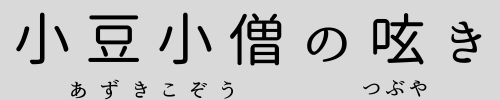
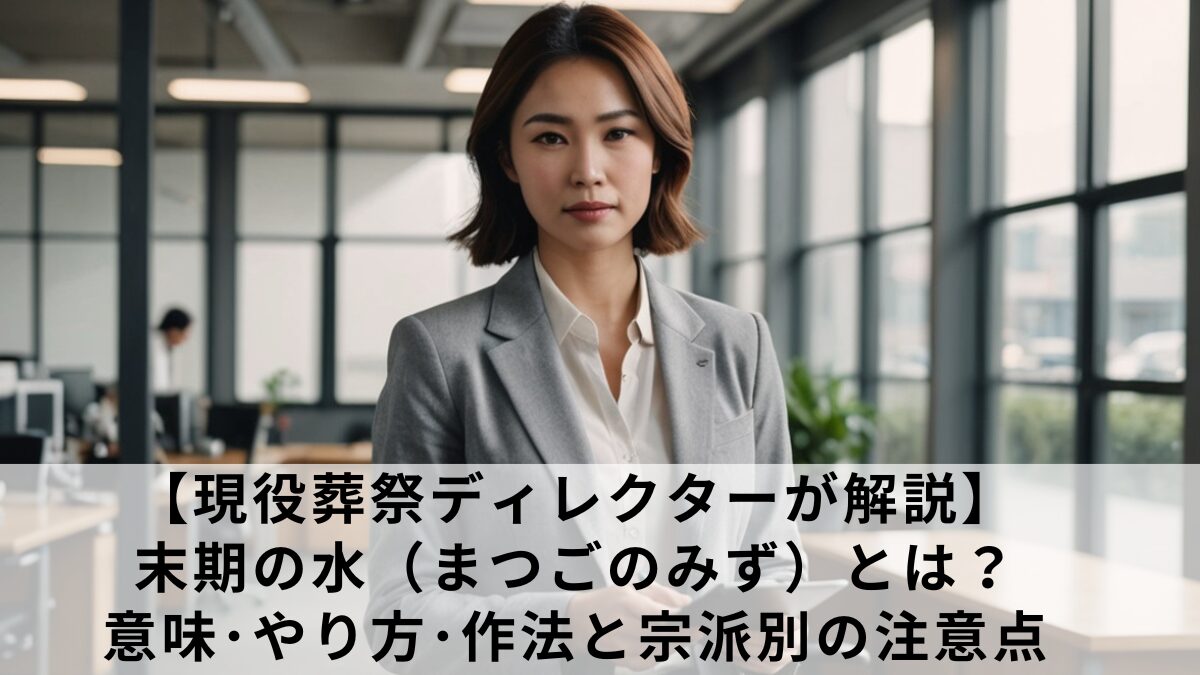


コメント