「エンバーミングってどれくらいの費用がかかるの?」
「見積書を見ても項目がよくわからない…」
葬儀の打ち合わせで初めてエンバーミングを提案され、その高額な費用に驚いて不安を抱えている方は少なくありません。
今回の記事では現役の葬祭ディレクターである私が、エンバーミングの費用相場と具体的な内訳を詳しく解説します。
さらに、高額請求などのトラブルを避け、後悔しないために知っておくべきポイントを紹介します。
エンバーミング費用の全国平均相場
エンバーミングの費用は、処置内容や依頼する葬儀社によって多少変動しますが、全国的な平均相場は15万円〜25万円で、IFSA(一般社団法人 日本遺体衛生保全協会)が定めているので業者間で大差はありません。
この費用はご遺体の状態が安定している場合の目安となります。
事故などによる損傷が激しい場合は、修復費用として追加料金が発生することもあります。
エンバーミングの価格差は、地域差や葬儀社の規模でなく、その葬儀社がエンバーミング施設を持っているかどうかの影響が大きいです。
施設を持たない葬儀社は、委託業者への委託費用が加算されるため、費用が高くなる傾向にあります。
見積書で確認すべき項目と料金の内訳
エンバーミングの価格は葬儀のプラン価格とは異なり、残念ながらほとんどの葬儀社が公表していません。
そのため、エンバーミング費用の確認・比較をしたければ、事前に問い合わせする必要があります。
依頼した後では葬儀社の言い値になってしまう可能性が高く、適正な価格かどうかの判断が難しくなります。
見積書では、主に以下の項目が含まれているか確認しましょう。
- エンバーミング費用: 処置自体にかかる費用
- 衣装:故人様が着る衣装の費用
- 搬送費: 安置場所からエンバーミングセンターへのご遺体の往復分の搬送費
- 安置費:葬儀(通夜)までの安置費用
- 納棺費:ご遺体を棺に納める費用を別に請求する業者があるので注意が必要です。
エンバーミングを依頼した場合、ご遺体の衛生管理・着せ替えから納棺まではエンバーマーが行うため、ドライアイスと湯灌の費用は原則として不要です。
もしエンバーミングの項目がある見積書にドライアイス・湯灌などの費用が計上されている場合は、葬儀社に確認が必要です。
「アフターケア」など不明な項目で、過剰なご遺体の処置で高額請求を謀ろうとする葬儀社の存在をSNSで確認できました。
また、日本国内で10万円未満でエンバーミングを行うことは不可能です。
安すぎる価格を提示された場合は、エンバーミングとは異なる簡易的な処置であるか、後から追加費用が発生する可能性を疑いましょう。
エンバーミングの費用を抑えるための方法
エンバーミングは高額なサービスだからこそ、本当に必要な場合のみ依頼すべきです。
しかし、エンバーミング施設を持つ葬儀社では、不要でも販売するケースがみられます。
費用を抑えるための最も確実な方法は、ご遺体の状態に応じてエンバーミングが本当に必要かを適切に判断し、必要な遺体にしかエンバーミングをしない葬儀社を遺族自身で探すことです。
- 一般的な処置だと説明する
2024年のエンバーミング実施率は5%にも関わらず、一般的な処置と虚偽の説明をする業者は、故人様や遺族の立場でなく、業者の都合で販売しようとしているのかもしれません。 - 不安を煽らない
「ご遺体が傷む」「腐る」といった言葉で不安を煽る担当者は、自社の利益を優先している可能性が高いです。 - 湯灌やラストメイクと比較して説明する
エンバーミングだけでなく、湯灌やラストメイクそれぞれのメリット・デメリットを丁寧に説明し、メリットだけを強調しないか確認する。
「ご遺族が衣装を持ち込めば、衣装代を抑えることができる」など、適切なアドバイスをしてくれる寄り添う姿勢の葬儀社を探すことが、結果的に無駄な費用を払い、後悔するのを防ぐ最善策となります。
SNSで以下の投稿を見かけました。
#遺体衛生保全自主基準 第1章1. ②には「依頼書への遺族による自署」が明記されている。代理署名は想定外。一般的には代筆するにしても委任状が必要だがそれもなし。それ以前に当時私は憔悴はしていたけれども署名ができないほどではなかった。
— mosrite 💙💛 owner (@mosriteowner) September 25, 2025
(画像は2025/9/25 #おはよう日本 から) https://t.co/xLULmFaz5F pic.twitter.com/YuEhKm8zdI
エンバーミングをするためには、遺族による同意書への署名が必要です。
同意書の内容をきちんと分かりやすく説明しているのか、担当者の姿勢で本当に必要なのか判断することも有効でしょう。
同意書への署名を省略する葬儀社(担当者)は、ご遺族(ご遺体)のことを考えずにエンバーミングを販売しているかもしれません。
日本とアメリカのエンバーミング費用を比較
日本のエンバーミング費用は、海外と比較すると高額だと指摘されています。
費用に大きな差がある背景には、それぞれの国の文化や業界構造の違いが関係しています。
エンバーミングの実施率が90%のアメリカと比較して解説します。
私が調査した情報: アメリカのエンバーミング費用は、単体の処置費用では平均500ドル〜1,200ドル(日本円で約7.5万円〜18万円)が相場で、日本の相場(15万円〜25万円)と比較すると安価です。
なぜアメリカのエンバーミングは安価なのか?
アメリカのエンバーミングが安価な理由の一つに、「葬儀業務の一環」として定着していることが挙げられます。
- 葬祭ディレクターがエンバーマーを兼務:
アメリカの多くの州では、葬儀の打ち合わせからエンバーミングの施術までを一人の葬祭ディレクターが担当することが一般的で、これにより業務の効率化が進み人件費が抑えられています。
- 高い普及率と競争:
エンバーミングの普及率が90%以上と高いため、施術件数が多く、高額な初期投資(設備費や資格取得費用)を一件あたりの価格に転嫁する必要が低くなります。
日本のエンバーミング費用が高額になる理由
一方、日本ではエンバーミング費用が比較的高額になる要因がいくつかあります。
- 専門職による業務分担: 日本では、エンバーミングの施術は専門のエンバーマーが行います。
葬儀社が依頼を受けてエンバーミング施設に搬送するため、搬送費や、エンバーマーの人件費が発生します。 - 専用施設の維持費: アメリカでは多くの葬儀社や葬儀会館(Funeral Home)が、エンバーミングを行うための専門施設を併設して、ご遺体の引き取りからエンバーミング・葬儀までを一つの場所で一貫して行います。
しかし、日本では全国に70施設程度しかない「エンバーミングセンター」に委託する方式が主流です。
そのため、施設の維持費だけでなく、センターまでの往復搬送費も費用に含まれることが多く、これが価格を押し上げる一因となっています。 - 低い普及率: 日本のエンバーミング普及率はまだ約5%と低く、施術件数が限られているため、スケールメリットによるコストダウンが働きにくいのが現状です。
エンバーマーと葬祭ディレクターの資格の違い
アメリカと日本における費用差の背景には、資格制度の違いも大きく関係しています。
| アメリカ | 日本 | |
| 資格の位置づけ | 州資格*多くの州で葬祭ディレクターと一体化 | 民間資格*IFSA(日本遺体衛生保全協会)認定 |
| 取得ルート | 葬儀科学大学(2~4年制)を卒業し、州試験に合格 | IFSA認定の専門学校(2年制)を卒業し、試験に合格 |
| 難易度 | 大学で専門教育と実習が必須のため専門性が高い | 合格率は50~60%(民間資格としては難易度が高い) |
| 取得費用 | 2年間で約450~750万円 | 2年間で約200万円 |
アメリカの方が取得費用は高額ですが、圧倒的な市場規模と施術件数により初期投資を効率よく回収できます。
まとめ
エンバーミングは、故人様との最期のお別れの時間を大切にしたいと願うご遺族には、非常に満足度の高いサービスです。
しかし、高額なサービスだからこそ、費用面で後悔しないための判断が重要です。
- エンバーミングと湯灌の目的の違いを理解する。
- エンバーミング施設を持っている葬儀社かどうかを確認する。
- 複数の葬儀社(3社ほど)から話を聞き、それぞれのメリット・デメリットを説明してくれるか見極める。
- 見積書の内容を細かく確認し、安すぎる価格を提示する業者には注意する。
これらの点を心がけ、故人様とご遺族にとって最適な選択ができるように、冷静な判断を心がけましょう。
今回の記事について、ご不明な点・ご意見などござましたらお問い合わせフォーム、下記のコメント欄よりお願いいたします。
同業他社、納棺師、エンバーマーの方などのご意見・ご指摘も大歓迎です。
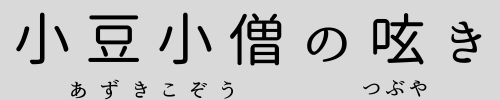
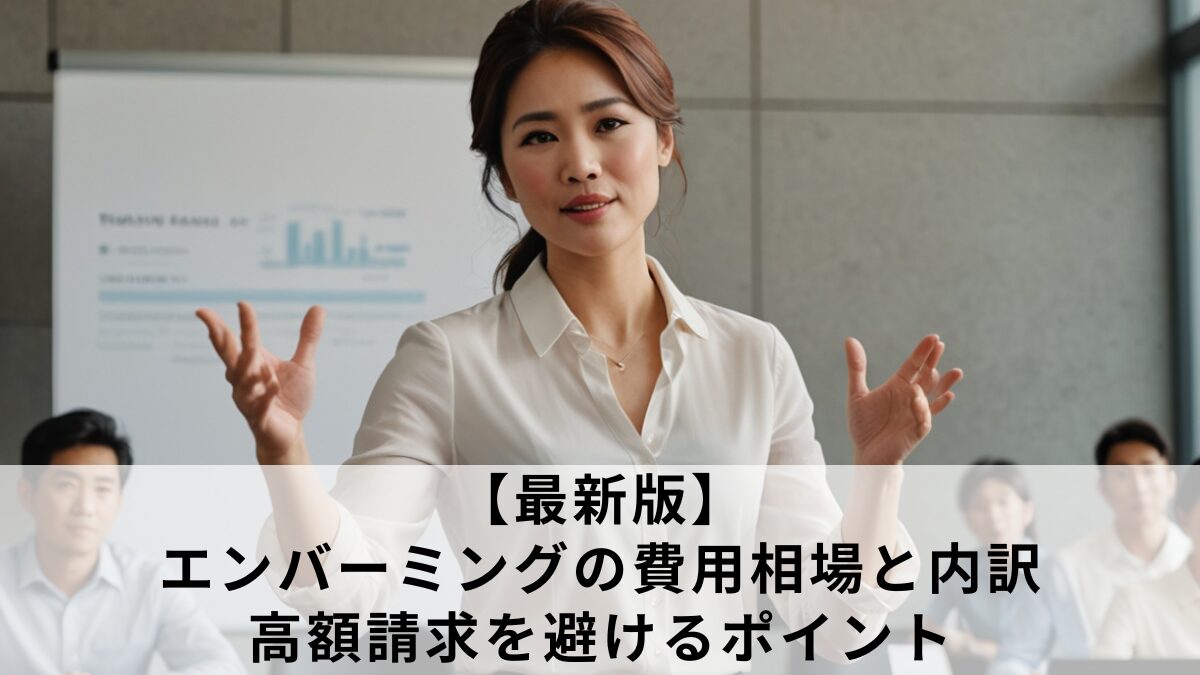


コメント