火葬場でご遺骨を骨壺に納める
「骨上げ(こつあげ)」
「拾骨(しゅうこつ)」
「収骨(しゅうこつ)」
日本の葬儀では、ご遺族や親族が協力して行われる大切な儀式です。
この際、火葬場で提供される対のお箸の長さや材質が異なっていたことはありませんか?
このような箸は「違い箸」と呼ばれ、普段目にする箸とは形状が異なります。
なぜ、このような特徴的な箸が使われているのでしょうか?
葬祭ディレクターとして私自身が収骨に立ち会う際に、時間が限られているので簡単な説明しかできません。
火葬場の職員が説明する場面でも、ご遺族は理解できないだろうと思うこともあります。
今回の記事では、「違い箸」の深い意味と由来を徹底的に解説します。
・火葬場で「違い箸」を使ったけど、意味を教えてもらっていなかった
・説明が大雑把過ぎてイマイチ意味が分からなかった
上記の方の助けになれば幸いです。
「違い箸」とは?
違い箸とは、その名の通り「異なる」箸のことで、具体的な特徴は以下の2点です。
- 一本が竹製、もう一本が木製など種類が異なる
- 長さが違う
ほとんどの場合、関西では火葬場が用意していて、一般の家庭で使う箸とは明らかに見た目が異なります。
なぜ「違い箸」を使う?知っておくべき3つの主な意味
この独特な「違い箸」には日本の死生観や文化に基づいた、いくつかの意味が込められています。
所説ありますが代表的な3つの意味を解説します。
「この世」と「あの世」の橋渡し(箸渡し)
本来、ご遺骨を骨壺に収める骨上げは男女二人一組で行われます。
一方が箸で骨を拾い、もう一方がその箸から箸へと骨を受け渡す「箸渡し」という作法が取られます。
「箸」と「橋」の音が同じであることから、故人が現世からあの世へ、迷うことなく安らかに旅立てるように、私たちが「橋渡し」するという意味が込められています。
ご遺族が故人を喪った悲しみを二人で分かち合うという説もあり、「箸渡し」の作法は二人一組になる必要があります。

違い箸を用いることで一人でも、二人一組で行う「箸渡し」と同じ意味が込められています。
死と穢れを避ける文化的背景
死を穢れ(けがれ)と捉える日本の価値観では、日常とは違う道具で扱うことや逆のことを行う「逆さごと」という風習が存在します。
このような風習には
「不幸が繰り返さないように」
「非日常的な出来事であることを強調する」
という願いが込められています。
- 普段は揃った箸を使うが、葬儀では違い箸を使う
- 着物や白装束を左前で着せる(生きている時は右前)
他にも「逆さ屛風」「逆さ水」などの「逆さごと」は、死という非日常を明確にして再び日常が平穏に戻ることを願う意味合いがあります。
そのために箸渡しは、
「合わせ箸(あわせばし)」
「拾い箸(ひろいばし)」
など言われ、日常生活において箸の作法ではマナー違反です。

違い箸も日常ではマナー違反とされますが、葬儀では故人への弔意を示す作法です。
急な出来事への対応
昔は急な訃報に際して、多くの揃った箸を用意するのが難しかったという現実的な理由も背景にあると言われています。
「あるものを持ち寄って対応した名残」という説です。
骨上げの作法と「違い箸」の深い関係
骨上げの際に行われる「箸渡し」は、故人のご遺骨を故人と縁の深い方々が「箸から箸へ」と渡していく作法です。
この作法は、故人の体を皆で支え、最後の共同作業として見送るという意味合いが込められています。

関西では違い箸を用いて箸渡しを行わず、各々が直接骨壺へ骨を納める場合も多くあります。
大切なのは作法ではなく、故人を想う気持ちです。
通常、足元から順に骨を拾い、最後に喉仏(のどぼとけ)の骨を拾い上げて、頭頂部の遺骨を載せます。つまり、骨壺の中で遺骨が立っている状態に近づけるように遺骨を納めます。
喉仏は一番大切な骨とされ、ご遺族の代表者である喪主が納めます。
一般的に喉仏とは男性の喉にある突起部分の名称ですが、火葬での「喉仏」とは、第二頸椎(首の骨)を指します。
別記事火葬後の“喉仏”は仏様の姿って本当?収骨で見えない理由を解説で、喉仏について詳しく説明しています。
地域や宗派による違いは?
違い箸を使うこと自体は、関西だけなく日本の多くの地域や宗派で共通して見られる習慣です。
- 骨壺の大きさ
- 骨上げの作法
- どの骨を先に納めるか
- 誰がどの骨を拾うか
上記の細かな点には地域差や宗派による違いがあります。
神道やキリスト教による違いもあります。

違い箸を使わない地域(火葬場)もあります。
ご自身の地域の慣習や宗派の作法について不安がある場合は、葬儀社の担当者に遠慮なく尋ねるようにしましょう。
プロの葬儀社であれば地域の風習に精通しており、適切なアドバイスを提供してくれます。
まとめ:違い箸の意味を知って、心を込めた見送りを
「骨上げ」で使われる「違い箸」は、単なる道具ではありません。
故人の安らかな旅立ち、そして不幸が繰り返されない、遺された家族たちの深い願いと伝統が込められた大切なものです。
この意味を知ることで、骨上げでより心を込めて臨めることを願います。
不安なことや疑問に思うことがあれば、遠慮なく葬儀社のスタッフに相談し、故人との最後のお別れを後悔なく迎えてください。
また、私を含めた葬儀社や火葬場のスタッフの説明でイマイチ納得できなかった方の役に立てれば幸いです。
今回の記事について、ご意見・ご指摘がございましたらお問い合わせフォーム、
下記のコメント欄からお願いします。
葬儀の際に不明だったこと、
葬儀社や僧侶などに聞けなかったことなど
教えてもらえれば今後の記事作りの参考にさせていただきます。
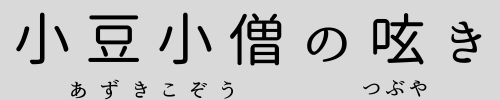



コメント