家族葬を検討しているけれど、何から手をつけていいか分からない…。
限られた時間の中で、どこまで準備できるの?
葬儀費用は?
どんな手続きが必要なの?
あなたは今、そんな漠然とした不安を抱えていませんか?
私自身は現役の葬祭ディレクターとして、突然のことで戸惑うご遺族を数多く見てきました。
関西圏では火葬場の予約状況や慣習的な背景から、ご逝去から火葬まで3日間で進行するケースが多く、短期間に多くの判断が求められます。
今回の記事では、あなたの不安を解消するため、関西における家族葬の具体的な流れを、費用や手続き、準備すべきことまで含めて徹底的に解説します。
この記事を読めば、いざという時でも慌てずに、大切なご家族とのお別れの時間を、心穏やかに過ごすことができるでしょう。
関西の家族葬の一般的な流れ(3日間)
【1日目】ご逝去当日|葬儀社へ連絡・搬送・安置
- 医師による死亡確認 → 死亡診断書を受け取る
- ご遺族が葬儀社に連絡(葬儀社は基本的に24時間対応)
- 寝台車で自宅または安置所へ移動
- 安置後に枕飾り(宗教形式に応じて)→葬儀社が対応
- 菩提寺(ご先祖から付き合いのある寺)があれば連絡
- 遺影写真の選定(スマホなどのデータでも可)
- 火葬場の空き状況確認 → 通夜・葬儀日程を決定
- 近親者への連絡(親族・関係者)
ワンポイント:
ご遺体の安置先は葬儀社の安置施設になることが多く自宅安置は減少傾向です。
自宅安置する際には、温度調節ができるエアコンがある部屋が必要。
葬儀社との連携が非常に重要となります。
菩提寺にも連絡して逝去の旨を伝えて、都合の確認も必要です。
【2日目】通夜当日|打ち合わせと通夜
- 葬儀社と詳細な打ち合わせ(参列人数・費用・会場準備について最終確認)
- 宗教者との段取り確認(布施の金額・式内容など)
- 親族が宿泊する場合の手配や食事の準備
- 納棺の儀(棺に納める品を用意)
- 通夜式(参列者の焼香の順番・喪主の挨拶)
- 通夜振る舞い(簡易な食事)
ワンポイント:
参列者が少なければ通夜振る舞いを省略するケースも多く
「軽食対応」または「手土産対応」で済ませることが増えています。
家族だけであれば喪主の挨拶も省略することもあります。
故人を自宅に安置していれば、式場に移動する時間の打ち合わせも必要です。
【3日目】葬儀・告別式・火葬・収骨・精進落とし
- 葬儀・告別式(読経・焼香・お別れ)
- 出棺 → 火葬場へ移動
- 火葬(1〜2時間) → 待機中に軽食または控室で休憩
- 収骨後:精進落とし
- 葬儀場または自宅へ戻る
- 自宅で後飾り(中陰祭壇)の設営
ワンポイント:
火葬場の設備や待合室の利用可否により式後の対応が異なります。
「初七日法要」を葬儀の当日に「繰り上げ法要」として行うことも一般的です。
出棺に先立って「式中初七日法要」で済ませる方も増えています。

後飾りの設営は葬儀社に依頼することも可能です。
後悔しないために知っておくべきこと
チェック1:家族葬の費用相場と内訳
家族葬にかかる費用は、地域や葬儀社によって異なります。
一般的には葬儀一式費用、飲食接待費、寺院関係の費用に分けられます。
葬儀社との打ち合わせで、明確な見積もりを出してもらい、どこまでが費用に含まれているかを確認することが重要です。
・全国展開している「小さなお葬式」の賢い使い方についてはこちら
チェック2:葬儀後も続く手続き・届け出リスト
葬儀が終わっても、法的な手続きや供養の準備は続きます。
- 役所にて戸籍関係手続き
- 年金・保険・銀行口座の名義変更や解約
- 法要(四十九日・納骨)の日程調整と案内
- 相続関係の手続き(必要に応じて専門家に相談)
まとめ:関西の家族葬で最も大切なこと
関西の家族葬は、他地域よりも進行が速く短期間での判断が求められます。
逝去の時間帯によっては「逝去から火葬まで2日間」も珍しくありません。
大切なことは、事前に信頼できる葬儀社とのつながりを持ち、家族間で流れと役割分担を共有しておくことです。
事前に葬儀社とのつながりを持つ必要性についてはこちら
「簡素で心あるお別れ」を実現するには、準備の早さと判断の落ち着きが何よりも鍵となります。
慣れていないことをするには、葬儀サービスのプロである葬儀社を積極的に利用していきましょう。
今回の記事について、ご意見・ご指摘がございましたらお問い合わせフォーム、下記のコメント欄からお願いします。
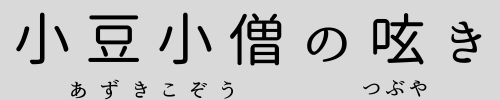
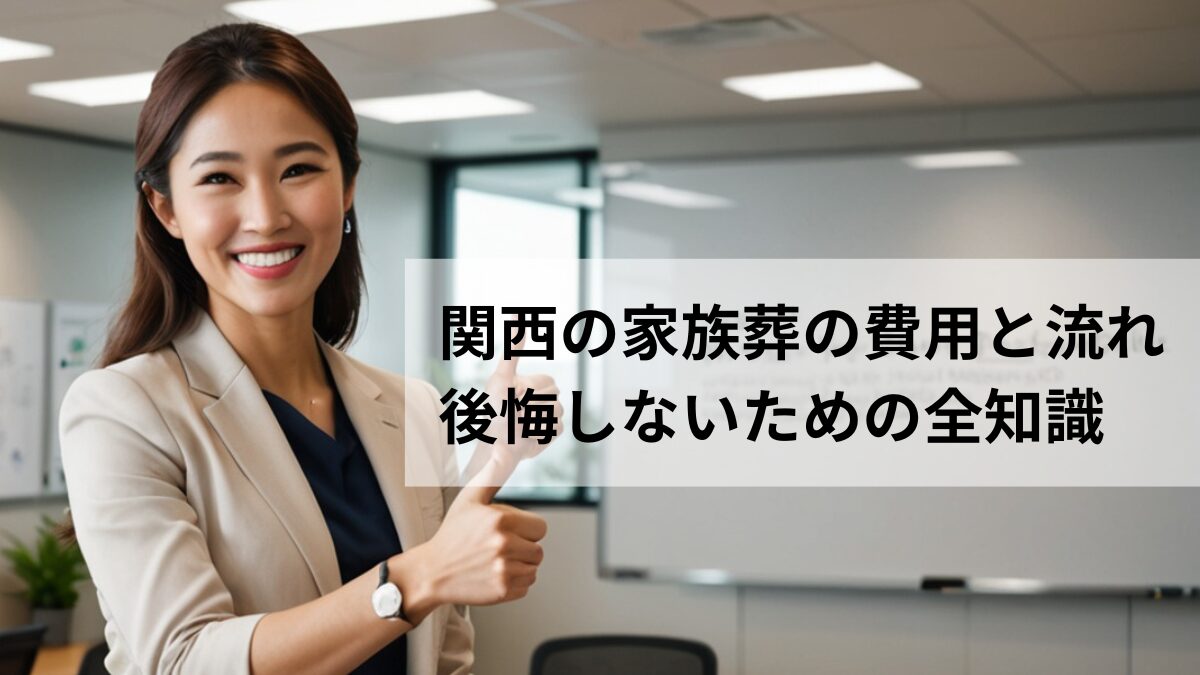


コメント