大切なご家族の遺骨を「分骨」したいと考えた際、葬儀社との打ち合わせで分骨の意向を伝えるので、その方法や手続きについて疑問や不安を抱えることはありません。
しかし、葬儀後に状況が変わり分骨する必要が生じた場合、「自分でしていいのか?」「どんな手続きが必要なのか」と戸惑うことでしょう。
この記事では、「分骨とは何か」という基本的な知識から、葬儀社に依頼せずに自分で分骨するやり方や具体的な手順、必須となる分骨証明書の取得方法、かかる費用、そして分骨後の注意点まで、現役葬祭ディレクターが徹底的に解説します。
手元供養のため、あるいは複数のお墓に納骨するためなど、あなたの分骨に関するあらゆる疑問を解消し、安心して故人様のお骨を扱えるよう、詳細な情報を提供します。
分骨とは?基本的な知識と分骨する理由・目的
まず、「分骨」がどのような行為を指すのか、そしてなぜ分骨を考える方が増えているのか、その背景から見ていきましょう。
分骨の意味と一般的な方法
分骨(ぶんこつ)とは、故人の遺骨を2つ以上の骨壺に分けて納めることを指します。

多くの場合すでに分骨すると決めていれば、火葬場で収骨する際に火葬場や葬儀社の担当者がその場で対応してくれます。
しかし、葬儀が済んだ後にご家族の状況や気持ちの変化、あるいは納骨先の事情などから、後日改めて分骨が必要になるケースも少なくありません。
例えば、自宅で手元供養をしたい、遠方に住む親族も遺骨を持ちたい、異なるお墓に納骨したい、といった多様な理由が挙げられます。
いったん骨壺に納められた遺骨を、ご自身で再び分けることは、手順さえ守れば決して困難なことではありません。
なぜ分骨するのか?主な理由と目的(手元供養、数か所への納骨、散骨など)
分骨を検討する理由は多岐にわたりますが、代表的な目的としては以下の点が挙げられます。
- 手元供養のため: 故人を常に身近に感じたいという思いから、遺骨の一部を自宅に置いて供養する方法です。
ミニ骨壺やペンダント、オブジェなどに納めることが多いです。「分骨 手元供養」という検索ニーズも高く、多くの方が選ぶ理由の一つです。 - 複数のお墓への納骨: 先祖代々のお墓と、新しく建立したお墓、複数の場所に納骨したい場合に分骨します。遠方に住むご親族が、各自の地域の墓地に納骨を希望するケースもあります。
- 散骨のため: 遺骨の一部を海や山などに散骨し、残りを手元供養やお墓に納骨するケースです。
散骨には環境への配慮や自治体の条例など、専門的な知識と手続きが必要になります。 - 家族間での分骨: 複数いるご兄弟がそれぞれ遺骨を持ち、故人を供養したいと希望する場合などです。
このように、分骨は故人を想うご遺族の多様な供養の形に対応するための、現代的な選択肢の一つとなっています。
分骨に必須の「分骨証明書」とは?取得方法と注意点
分骨を行う上で最も重要となるのが「分骨証明書」です。
これは、お墓や納骨堂などの施設に遺骨を納骨する際に必要となる書類であり、その役割は火葬許可証と同じです。
分骨証明書と火葬許可証の役割の違い
「火葬許可証」は、ご遺体を火葬する際に自治体から発行される書類で、火葬後には「火葬済」の押印がされ、これが納骨・埋蔵する際の許可証となります。通常は、一人に対して1枚発行されます。
上記のことは、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)で定められています。
一方、「分骨証明書」は、火葬済の遺骨を2個以上の骨壺に分ける場合に、分けた遺骨の数だけ必要となる証明書です。「火葬済証明書」と呼ばれることもありますが役割は同じです。
分骨した遺骨を納骨する際には、この書類が必要です
手元供養で自宅に安置するだけの場合は必ずしも必要ではありませんが、後に納骨する可能性を考えると取得しておくのが賢明です。
【状況別】分骨証明書の取得方法(火葬場での分骨、葬儀後の分骨、墓地・納骨堂からの分骨)
分骨証明書の取得方法は、分骨を行うタイミングや遺骨の安置場所によって異なります。
- 火葬場で収骨する際に分骨する場合: 葬儀社の担当者が、火葬場で分骨を希望する旨を伝え、火葬場側で必要枚数の分骨証明書の発行手続きを行います。ご遺族は特に手続きを行う必要はありません。*発行できない火葬場では、後日ご遺族自身が役所などでの手続きが必要です。
- 葬儀が済んでから自宅にある遺骨を分骨する場合: ご自身で分骨する際には、ご自身で分骨証明書の発行手続きを行う必要があります。
利用した火葬場、もしくはその火葬場を運営する市区町村の役所が発行します。 - お墓や納骨堂に納骨した遺骨を分骨する場合: すでに納骨されている遺骨を分骨する場合は、その墓地や納骨堂の管理者が分骨証明書を発行します。遺骨を一度取り出し、再度納骨する際に必要となります。
発行手数料と必要書類、申請窓口(火葬場・役所・管理者)
分骨証明書の発行には、無料~数百円程度の発行手数料がかかるのが一般的です。
申請時には、身分証明書(運転免許証など)や、故人様との関係を示す書類(戸籍謄本など)、火葬許可証(原本またはコピー)の提示を求められる場合がありますので、事前に発行元に確認しておきましょう。
- 葬儀後の自宅での分骨: 利用した火葬場、もしくは火葬場を運営する市区町村の役所の担当課(戸籍課や環境課など)
- 納骨後の分骨: 遺骨が納められている墓地や納骨堂の管理事務所
火葬場は市役所とは異なり、朝9:00から17:00までしか電話が繋がらないことが多く、友引や特定の日に休場している場合もあります。
事前に電話で連絡を取り、発行場所、必要書類、手数料、受付時間などを確認しておくことをお勧めします。ほとんどの場合、即日発行してくれます。
管理者が常駐していない墓地では、発行に時間がかかることもあるので、電話等で確認しておきましょう。
分骨証明書に関するよくある質問(再発行、有効期限など)
- 分骨証明書の有効期限は? 分骨証明書には有効期限がありません。取得しておけば、将来的に納骨先が変わるなどの状況でも安心して使用できます。
そのため、遺骨と一緒の場所など、紛失しないよう大切に保管しておくことが重要です。 - 分骨証明書を紛失したら? 万が一紛失した場合は、発行元である火葬場または市区町村の役所に連絡して、再発行の手続きを依頼してください。再発行には手数料がかかる場合があります。
自分でできる!葬儀後の「分骨のやり方」の手順と準備物
葬儀が済み、自宅に遺骨が1つの骨壺に納められている状況から、ご自身で分骨する手順を具体的に解説します。今回は、小さい骨壺に追加で取り分ける方法を想定しています。
必要なものリスト(骨壺、割り箸、手袋など)
自分で分骨する際に用意すべきものは以下の通りです。
必要なものリスト(骨壺、割り箸、手袋など)
自分で分骨する際に用意すべきものは以下の通りです。
- 新しい骨壺(分骨用の小さい骨壺): 遺骨を分ける数だけ必要です。「分骨容器」として、2寸や3寸程度のミニ骨壺が適しています。葬儀社でも購入できますが、Amazonなどの通販サイトでは種類が豊富で割安なものも多く、事前に購入すれば費用を抑えられます。
- 白手袋: 素手で遺骨を触ることに抵抗がある場合に。
- 清潔な割り箸: 遺骨を拾い上げる際に使用します。
- 白い布または半紙: 作業台に敷いて、遺骨が散らばらないようにします。
- アルコールシートやタオル: 作業後の手や道具を清拭するため。
分骨する遺骨の量と「部位へのこだわり」について
火葬場で収骨と併せて分骨を行う場合は、火葬場や葬儀社の職員が、故人様の「喉仏(実際には第二頸椎の一部)」や「指先の遺骨(お地蔵様の形に似ているとされる)」など、特定の部位を探して分骨容器に納めてくれます。これは、遺骨に関する専門知識と経験がなければ難しい作業です。
ご自身で分骨する際は、特定の部位を探し出すことは困難であり、無理に行うと遺骨を傷つけてしまう可能性もあります。
部位へのこだわりは諦め、容器に納めやすい大きさの遺骨を優しく取り分けるようにしてください。
遺骨は非常に脆いものですから、慎重に作業を進めましょう。
骨壺から遺骨を取り分ける具体的な手順と注意点(衛生面、慎重な作業)
- 作業場所の準備: 清潔で安定した場所を選び、白い布や半紙を敷いて遺骨が散らばらないようにします。
- 骨壺の開封: 現在遺骨が納められている骨壺の蓋を、ゆっくりと慎重に開けます。
- 遺骨の取り出し: 清潔な割り箸や専用のピンセットを使用し、分骨用の小さな骨壺へ遺骨を移し替えます。遺骨を粉状にする必要はありません。
- 新しい骨壺への納骨: 分けた遺骨を新しい骨壺に納め蓋を閉めます。
- 元の骨壺の蓋を閉める: 分骨後に残った遺骨が納められている元の骨壺も、丁寧に蓋を閉めてください。
- 清掃: 作業後は、使用した割り箸などを適切に処分し、作業場所をきれいに清掃します。
注意点:
- 遺骨はデリケートなものです。無理な力を加えたり、急いで作業したりしないようにしてください。
- 衛生面にも配慮し、手袋の使用を検討しましょう。
- 遺骨の取り扱いには、ご自身の精神的な負担も伴います。
無理だと感じたら、無理せずに葬儀社や専門家に相談することも検討しましょう。
【状況別】注意が必要な分骨と専門家への相談
自分で分骨できるとはいえ、遺骨の状態や納骨状況によっては専門家への依頼が推奨されるケースもあります。
墓地に納骨している遺骨の分骨

墓地に納骨している遺骨は、時間が経つとカビが生えるなど、状態が悪くなっているかもしれません。
状態が悪い遺骨は、分骨する前に洗浄して乾燥と、専門の技術が必要です。
お墓から取り出す場合は、構造を理解しておかないと事故の元になるので、墓石を建立した業者に任せた方が無難です。
分骨後の「余った遺骨」の供養方法(火葬場、永代供養)
分骨が済んでから元の骨壺に残った遺骨(余った遺骨)の供養方法も事前に考えておく必要があります。
特に以下のようなケースでは、余った遺骨の納骨先に困ることがあります。

- 一心寺(大阪)に納骨したいが、骨壺の大きさに上限があるため、一般的なサイズの骨壺に納めた遺骨では全て納められない。
(参考【徹底解説】一心寺の永代供養「お骨佛」とは?費用・納骨の流れ・注意点) - 新しく選んだ納骨場所には骨壺の大きさに規定があり、小さいサイズに変更しなければならない。
上記のような事例では、分骨した後の余った遺骨は以下の方法で供養を検討できます。
- 利用した火葬場に相談: 一部の火葬場では、余った遺骨を引き取ってくれる場合があります。
利用した火葬場に連絡し、対応してもらえるか確認してください。 - 永代供養墓・納骨堂への納骨: 火葬場で対応してもらえない場合は、永代供養を行っている霊園や納骨堂に納めるのが一般的です。
Googleなどで「永代供養 大阪」「永代供養 兵庫」といったキーワードで検索し、探してみましょう。数万円ほどの費用はかかりますが、確実に供養してもらえます。
手元供養で分骨する際のポイント
分骨の中でも、特に「手元供養」を目的とするケースが増えています。
手元供養で遺骨を自宅に安置する場合の注意点を見ていきましょう。
手元供養のメリットと選択肢(自宅安置、ミニ骨壺、アクセサリーなど)
手元供養の最大のメリットは、故人を常に身近に感じられることで、自宅に安置するアイテムや、以下のような多様な選択肢があります。
- ミニ骨壺: 数cm~10cm程度の小さな骨壺で、リビングや寝室など、お好みの場所に置いて供養できます。
- メモリアルペンダント・リング: 遺骨の一部を加工し、身に着けられるアクセサリーにする方法です。
- 遺骨オブジェ: 遺骨を特殊な素材に練り込み、ガラスや陶器などのオブジェとして飾る方法です。
どの方法を選ぶかは、故人様への想いやご自身のライフスタイルに合わせて検討しましょう。
手元供養でも分骨証明書が必要な理由と保管の重要性
「手元供養で自宅に安置するだけだから、分骨証明書は不要なのでは?」と思われるかもしれません。
しかし、たとえ現時点では自宅で供養するつもりでも、将来的に供養の継承者が変わったり、ご自身のライフスタイルの変化によって、遺骨を別のお墓や納骨堂に納めたいと考える可能性は十分にあります。
手元供養を目的とした分骨でも、分骨証明書は取得しておくことを強くお勧めします。
分骨証明書には有効期限がないため、一度取得しておけば将来のどのような選択にも対応できるので、大切に保管しておきましょう。
葬儀社に頼まず分骨する際の費用削減と時間のメリット
葬儀社に分骨を依頼すると、葬儀がすでに済んでいるため、その手続きや移動にかかる手数料が請求されることがあります。
葬儀社は日々の葬儀業務を優先するため、分骨対応に時間がかかり、ご遺族が希望するタイミングでの対応が難しい場合もあります。
自分で分骨する方法を理解していれば、このような追加費用を抑え、ご自身の都合の良いタイミングで、故人様とじっくり向き合いながら分骨を行うことができます。
安心して分骨するための確認事項
手順通りに進めれば、自分自身で分骨することは決して困難ではありません。
分骨証明書の発行手続きで若干の手間はかかりますが、不都合なく取得できるでしょう。
- 分骨証明書の取得: 発行元(火葬場または役所、墓地管理者)を事前に確認し、必要書類と手数料を準備しましょう。
- 分骨容器の準備: サイズや種類を検討し、事前に購入しておくとスムーズです。
- 丁寧な作業: 遺骨はデリケートです。心穏やかに、丁寧に作業を進めてください。
- 書類の保管: 分骨証明書には有効期限がないため、紛失しないよう大切に保管してください。数年先に納骨する際には、この証明書が不可欠となります。
ご不明な点・ご意見などござましたら、お問い合わせフォーム、下記コメントよりお願いいたします。
分骨に関するよくある質問 (FAQ)
Q1・分骨に法的な問題はない?
分骨証明書があれば問題なく納骨することができます。故人様の遺骨は、ご遺族の意思に基づき供養されるべきものとされています。
Q2・分骨した遺骨はいつまでに納骨する?
分骨した遺骨をいつまでに納骨しなければならないという明確な法的期限はありません。ご自宅での手元供養であれば、ご自身が望む期間、安置し続けることが可能です。
また、お墓や納骨堂への納骨も、ご遺族の都合や準備が整ったタイミングで行えば問題ありません。大切なのは、故人様への供養の気持ちと、ご遺族が納得できる形でお見送りをすることです。
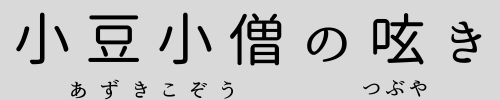
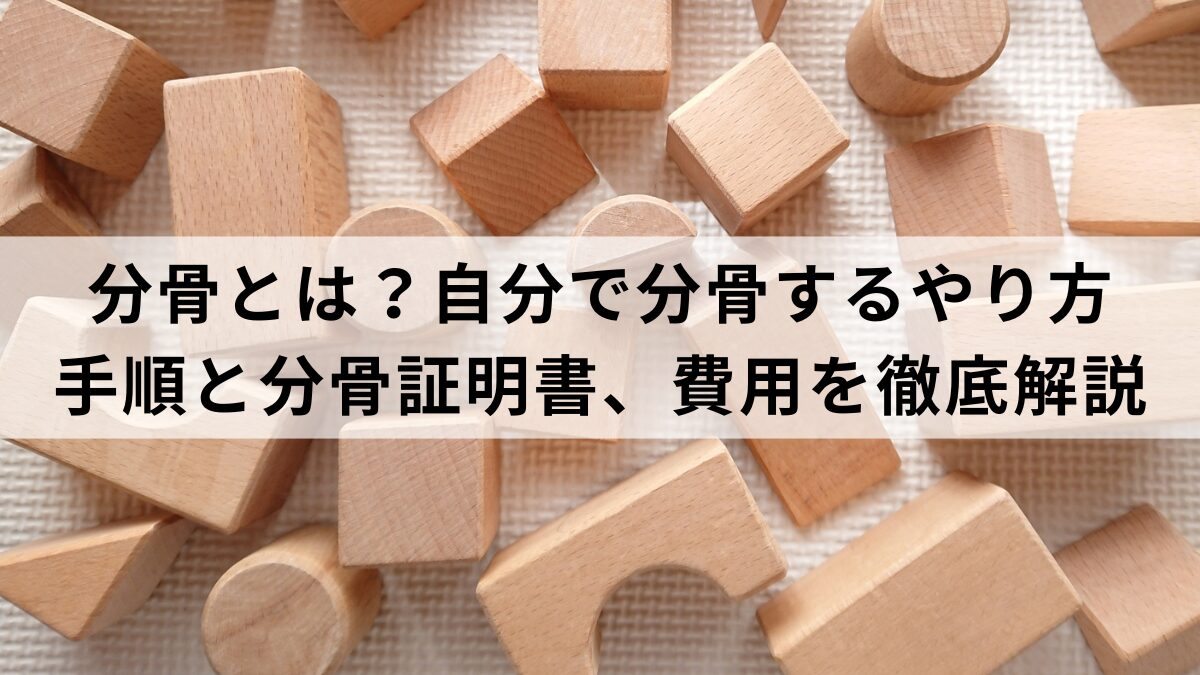


コメント